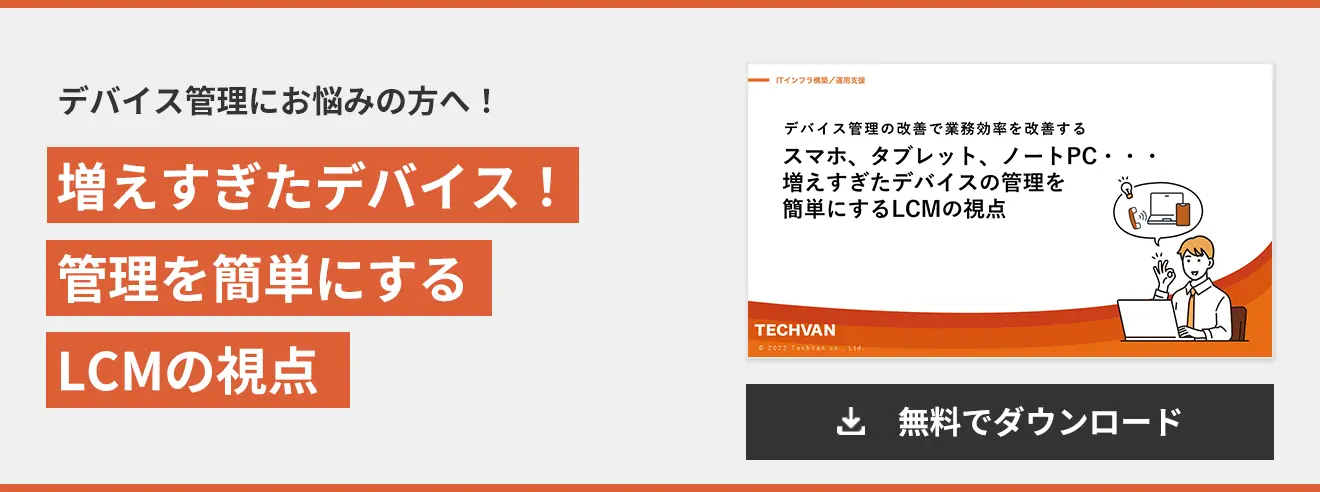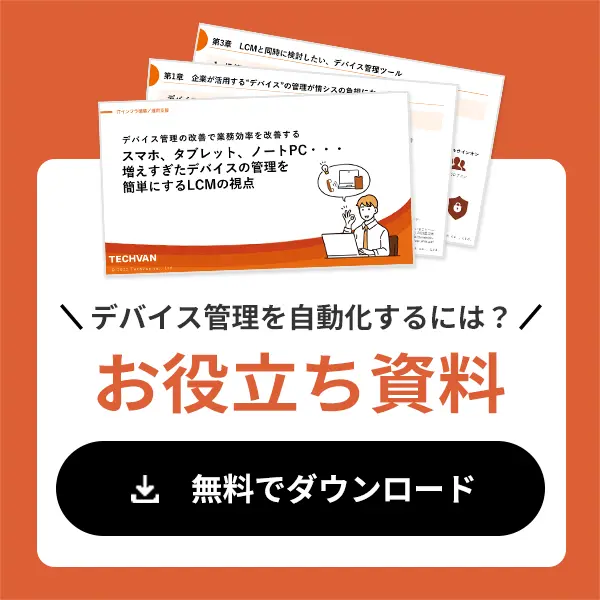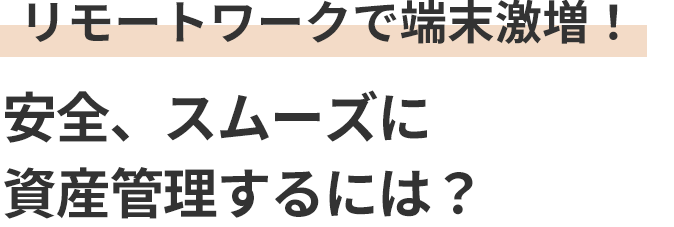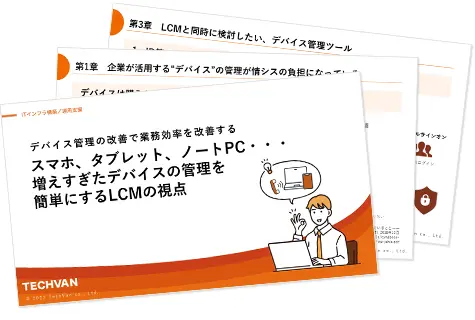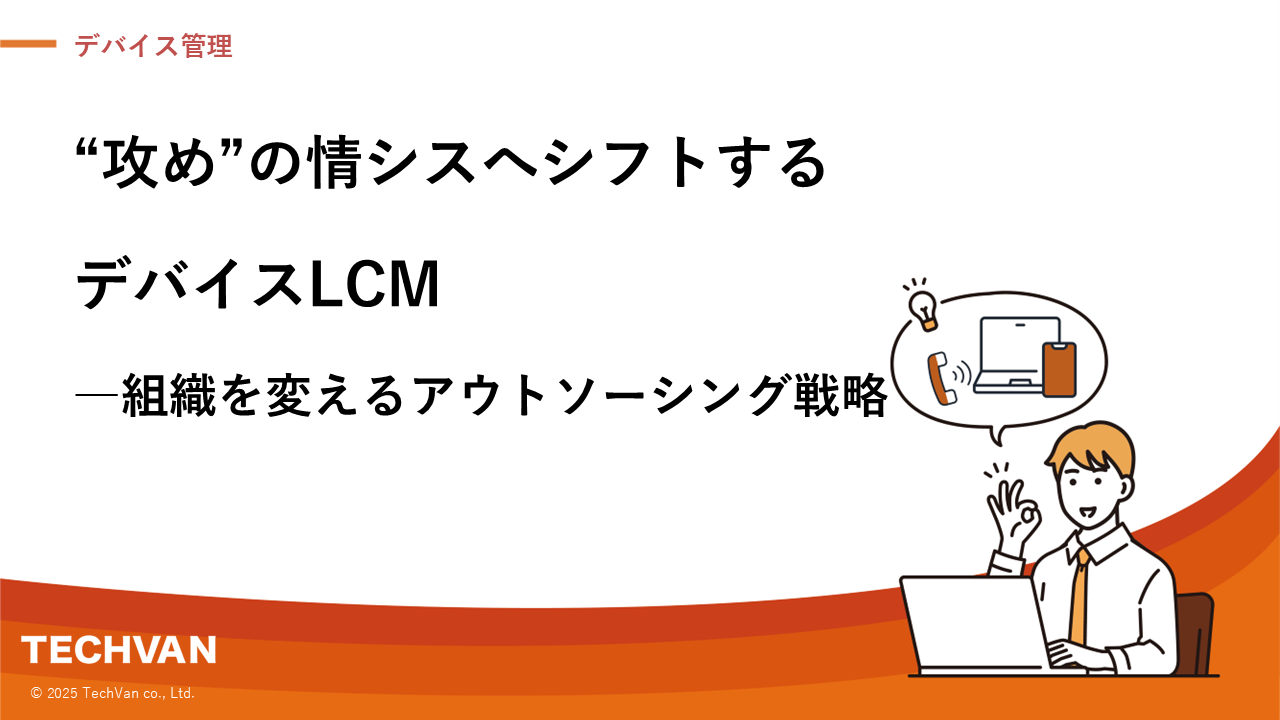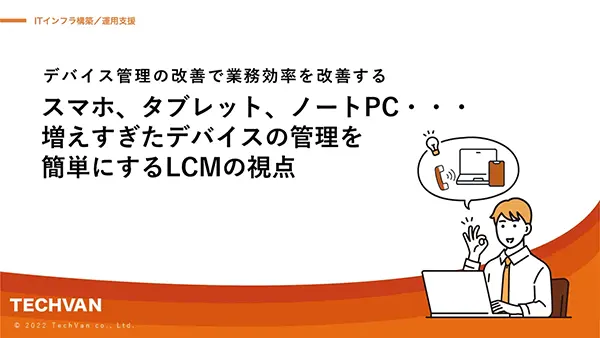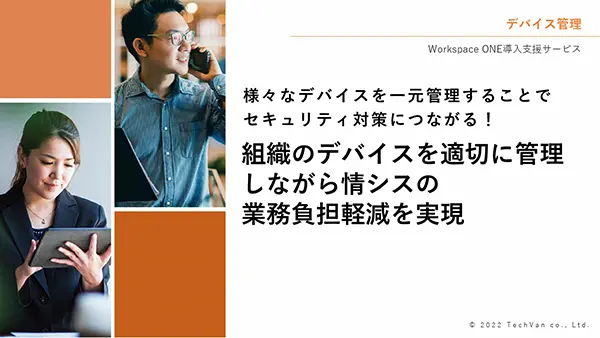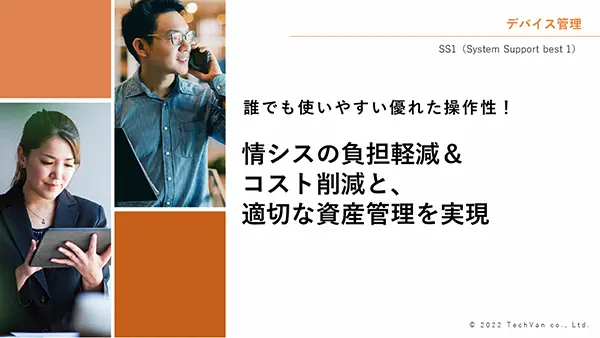PCの導入から廃棄・更新までを一括管理する「PC LCMサービス」は、コスト削減やセキュリティ強化、業務効率化を実現する手段として多くの企業で導入が進んでいます。
そこで本記事では、PC LCMの基本から具体的な提供内容、導入メリット、セキュリティ対策、成功事例、今後のトレンドまでを徹底解説。自社のIT資産管理を最適化するためのポイントもご紹介します。
PC LCMサービスとは何か
PC LCMサービスは、企業のIT資産であるPCに関するあらゆるプロセスを包括的に支援するアウトソーシング型のソリューションです。
現在、多くの企業がIT資産管理の外部委託を進めており、PC LCMサービスは社内のIT運用負荷軽減、セキュリティ向上、そしてコスト最適化を図る手段として注目を集めています。
LCMの中でも特にPCといったエンドポイントデバイスは、業務の効率や情報の機密性と直結するため、包括的かつ戦略的な管理が求められています。
ここでは、LCMの基本的な定義と、PC LCMサービスの概要について詳しく解説します。
LCMの意味と定義
LCMとは「Life Cycle Management」の略で、「製品やサービスの企画・導入から、運用・保守、そして廃棄に至るまでの全体的な管理プロセス」を指します。
PC LCMにおいては、IT資産・特にPCや周辺機器が以下のプロセスを経てライフサイクル管理されます。
| フェーズ | 主な内容 |
| 導入企画・調達 | 使用目的・業務要件に応じた機種選定と機器の購入 |
| キッティング・展開 | OS設定、セキュリティソフト導入、ネットワーク設定の事前構築 |
| 運用・管理 | IT資産管理、障害対応、セキュリティパッチ適用、ソフトウェア管理 |
| リプレース・廃棄 | 老朽化した機器のデータ消去、適切な廃棄処理またはリプレース |
このように、PC LCMサービスは「点」ではなく「線」——つまりIT資産のライフサイクル全体にわたる流れの管理で、単なるITサポートとは異なる戦略的IT統制を担うのです。
PC LCMサービスが注目される背景
昨今の働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進、さらにはテレワーク・リモートワークの普及は、企業におけるIT資産管理を複雑化させています。
業務環境が多様化する中で、さらに以下のような背景からPC LCMサービスへの需要が高まっています。
- 社員のPC利用環境が社内外に広がり、端末管理が煩雑化
- IT部門のリソースが不足し、定期的なメンテナンスや更新作業の対応が困難
- セキュリティガバナンス強化の必要性(経済産業省の「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」でもPCなどのIT資産管理の徹底が推奨されている)
- BCP(事業継続計画)強化の観点から、迅速に再展開可能なIT体制が求められている
また、複数の拠点やテレワーク・リモートワーク環境下への端末展開には専門知識と多くの工数がかかるため、その業務を外部事業者に任せるアウトソーシング戦略が加速しています。
特に、大企業を中心にITエンジニアの確保が困難になっている現状では、LCMを包括的に外部化し、社内はコア業務に人材を集中させるスタイルが主流です。
このような背景を踏まえると、今後の企業運営においてPC LCMサービスは「コスト削減手段」ではなく「事業継続・組織競争力維持の基盤」として不可欠なITインフラマネジメントの一部であるといえます。
PC LCMサービスの主な提供内容と実施範囲
PC LCM(ライフサイクルマネジメント)サービスは、企業が保有するPCなどのIT資産を、導入から廃棄までの全ライフサイクルにわたって一元的に管理し、業務効率化や運用コストの最適化、セキュリティ強化を実現するための支援を行うサービスです。
導入時のキッティング作業から、運用中の保守・サポート、そしてリプレースおよび廃棄処理まで含め、幅広い工程をカバーします。
そこで、PC LCMサービスにおける主な提供内容と、その実施範囲について項目別に詳しく解説します。
テクバンのLCMサービスとは?
資産管理と在庫管理
資産管理と在庫管理は、PC LCMサービスの中核的な要素です。企業にとって、どの部署に何台のPCが配備されているのか、OSやソフトウェアのバージョン状況はどうかといった情報を正確に把握することは、ITガバナンスの向上やコスト最適化に直結します。
サービス提供事業者は、専用の資産管理ツール(例:System Support best1(SS1)、SKYSEA Client Viewなど)を用いて、ライフサイクルごとの資産台帳を作成・管理。リアルタイムでの在庫状況の可視化や、リース満了・契約更新時期を自動通知するなどによって、適切な再配備や廃棄判断が可能となり、余剰在庫の削減と資産有効活用が進みます。
IT資産管理ツールについて詳しくはこちら。
▼IT資産管理ツール比較10選! 機能、タイプ別の選び方も紹介
キッティングと展開作業
キッティングとは、新たに導入するPCを、業務で即利用できる状態にセットアップする工程のことです。具体的には、OSインストール、必要なアプリケーションの導入、ユーザーアカウント設定、ネットワーク接続、セキュリティポリシー反映などを指します。
また、近年のリモートワーク普及に対応するため、「ゼロタッチキッティング」や「Windows Autopilot」などを活用したクラウドベースのキッティング作業が導入され、全国拠点への迅速な展開が可能になっています。
このため、地方拠点や在宅勤務者へのPC配布もスムーズに行えるようになり、業務開始までのリードタイムが短縮されます。
キッティングについてさらに詳しくはこちら。
▼キッティング作業とは? 作業手順、注意点、効率化のポイントを解説!
ヘルプデスクとユーザーサポート
PC利用における問い合わせやトラブル発生時の対応を行うため、LCMサービスではヘルプデスクが含まれます。ヘルプデスクはIT部門の負担を軽減し、従業員の生産性低下を避ける重要な要素です。
| 対応内容 | 例 | 対応時間 |
| ソフトウェアトラブル対応 | Office製品のエラー、VPN接続不良など | 平日9:00〜18:00(事業者により24時間対応も可能) |
| ハードウェア相談 | 起動不良、バッテリー異常、周辺機器不具合 | オンサイトサポートまたはリモート対応 |
| OSやセキュリティ更新 | Windows Update、ウイルス定義ファイル更新 | 自動スクリプト適用や遠隔制御での対応 |
保守・修理・デバイス交換
PCが故障した場合やデバイス部品の劣化時には、迅速な修理やダウンタイムを抑えた交換対応が必要です。
LCMサービスでは、あらかじめ定められたサービスレベル(SLA)に基づき、オンサイト修理・引き取り預かり修理・代替機の提供のいずれかの方法で対応します。
特に重要な業務を行う部署では、事前にキッティング済みの予備端末を常備しておく「ホットスワップ」方式を採用することで、従業員の業務停止を最小限に抑えるケースが増えています。
また、正規メーカーによる修理パートナーとの連携により、保証期間外でも高品質な修理サービスを受けることも可能です。
リプレースとデータ消去
PCの使用年数が経過し、更新が必要になった段階で行われるのが「リプレース」です。
これは、パフォーマンス低下やセキュリティリスクの高まり、メーカーによる保守終了などを考慮して、4〜5年を目安に実施されるのが一般的です。
リプレースでは、既存端末の回収と同時に、新しいPCとの入れ替え作業、必要なデータの移行を一括して行います。
この際、旧端末のデータ消去は特に重要なプロセスです。国際的なデータ消去規格(例:NIST SP800-88)に準拠した消去方式を採用する事業者もあり、情報漏えい対策として企業の信頼性を維持します。
| 対応項目 | 具体内容 |
| データ移行 | ユーザープロファイル、アプリケーション設定などの自動コピー |
| データ消去 | NSA方式、DoD5220.22-M方式などのソフトウェア消去ツール使用 |
| 機器廃棄 | リサイクル認定業者による法令遵守の処理 |
環境面への配慮として、PC回収後に適切なリサイクルを行う「グリーン調達方針」に対応したサービスも増えており、CSR(企業の社会的責任)への配慮も評価ポイントとなっています。
企業がPC LCMサービスを導入するメリット
従業員の働き方が多様化し、DXが進む中、社内のIT管理体制を効率化・最適化する必要性が増しています。
そのため、PC LCMサービスは多くの企業にとってコスト効率だけでなくセキュリティや運用面でも大きな優位性を発揮する施策として注目されています。
ここでは、企業がPC LCMサービスを導入することで得られる主なメリットについて、具体的かつ多角的に解説します。
コスト削減の具体的なポイント
PC LCMサービスは、IT資産の導入から廃棄までの全工程をアウトソースすることで、企業側の直接的、間接的なコストを削減できます。特に、PCの選定、発注、初期設定、配布、保守、回収、処分といった全フェーズで人的リソースや管理工数を大幅に削減できる点が特徴です。
| 工程 | 従来のコスト要因 | LCMサービスによる削減内容 |
| PCの調達 | 機種選定・メーカーごとの調整 | 最適な構成の一括調達によるコスト圧縮 |
| キッティング | 人件費、作業場の確保 | 代行により社内工数とスペース削減 |
| 保守・修理 | 故障時の都度対応による費用増 | 保守契約により予算化が可能 |
| 廃棄処理 | 機密情報の処理、産業廃棄物処理対応 | 法令準拠のワンストップ廃棄でコスト低減 |
また、定量的なコストの最適化だけでなく、運用の効率化により間接費の削減も実現できます。
IT部門の業務負荷軽減
PC LCMサービスの導入により、社内のIT情シス部門は、機材まわりの煩雑な管理業務から解放され、戦略的かつ価値の高い業務にリソースを集中しやすくなります。
特に、中小企業や限られた人員で運用する情シス部門では、このメリットが顕著です。
キッティングや修理対応、在庫・資産台帳の管理といった、定型的で工数がかかる業務が外部に委託できるため、IT人材の負担は大幅に軽減されます。
さらに、PCの全ライフサイクルを一元的に可視化・管理できるプラットフォームが提供されることが多く、マルチベンダー環境でも情報が整い、IT部門の運用効率も向上します。
こうした観点からも、リソースの再配分により組織全体としてのIT戦略遂行能力を高める効果が期待できます。
情報システム部門の本来の役割、あるべき姿について詳しくはこちら。
▼情報システム部門のあるべき姿と今後求められる役割とは? 攻めのDXを実現する「戦略的アウトソーシング」を解説
業務の効率化と生産性の向上
PC LCMサービスは単なるコスト削減の手段にとどまらず、従業員の業務環境の整備にも寄与し、組織全体の生産性向上に貢献します。
例えば、新入社員の入社に合わせてキッティングされたPCがスムーズに配布されることにより、初日から即戦力となる業務環境が整うため、教育研修にも良い影響があります。また、PCの不具合が発生した際には迅速な代替機提供や修理手配が可能となるため、業務の停滞を防ぎます。
さらに、サービスによっては、ソフトウェアの配布やデバイス状態の遠隔監視などを柔軟に実施できるため、テレワークや在宅勤務が一般化した現代の労働環境にも適応します。
結果として、業務の継続性と従業員の満足度を高め、働きやすいITインフラの構築が可能となるのです。
PC LCMサービスがセキュリティ強化につながる理由
企業の情報管理において、近年ますます重要性を増しているのがセキュリティ対策です。テレワークの普及やクラウドサービスの浸透により、従業員が利用するPCやモバイルデバイスの管理は一層複雑になっています。
PC LCMサービスは、これらのIT資産を包括的に管理することでシステムの脆弱性を低減し、全社的なセキュリティレベルを底上げするという大きな役割を担っています。
この章では、PC LCMサービスがどのようにしてセキュリティ強化につながるのか、3つの観点から解説します。
OSやソフトウェアの最新化と統一化
多くの企業では、部門ごとに異なるOSバージョンやソフトウェアが混在しているケースが見られます。
これにより、パッチ適用のタイミングがずれる、古いバージョンのまま放置されるといったリスクが常に存在しています。
しかし、PC LCMサービスを導入することで、全社的に利用するOSのバージョンや業務アプリケーションの構成を統一することが可能になります。
特にWindowsを中心とした環境では、定期的なアップデートとパッチ適用が情報漏えいやマルウェア侵入の最も基本的かつ重要な防御施策とされており、IT部門だけでこれを手動で実施するのは現実的ではありません。
LCMサービスは、こうした更新作業を自動化・一元管理する機能を備えており、意図せぬソフトウェアの脆弱性を未然に防ぎます。
さらに、使用するソフトウェアのライセンス管理も一括で行えるため、非正規ソフトウェアの使用やライセンス違反によるリスクの低減にも寄与します。
情報漏えいリスク対策(データ消去、リモート制御)
従業員がPCを不注意で紛失したり、退職者がデバイスを持ち出すなどのインシデントは、情報漏えいの大きな原因になります。
こうした事態にも対応できるよう、PC LCMサービスでは厳格なデータ消去ポリシーや遠隔制御機能があらかじめ組み込まれているケースが増えています。
具体的には以下のような提供内容が含まれることが一般的です。
| 対策項目 | 具体的な施策 | セキュリティ強化への貢献 |
| データ消去 | 国際基準準拠のデータ消去ツールを使用 | 復元不可能な状態で旧端末を廃棄 |
| リモートロック/ワイプ | 紛失・盗難時に管理者が遠隔で端末を制御 | 情報漏えいリスクを迅速に遮断 |
| ログ管理 | 操作履歴およびアクセス記録の管理 | 不正行為の可視化と証跡保全 |
例えば、モバイルデバイス管理(MDM)ツールと連携したPC LCMサービスを採用すれば、紛失時でも端末を遠隔でロックでき、内部情報の流出を最小限に抑えることが可能です。また、PCの廃棄や返却時には、米国国防総省(DoD)準拠の方式に沿ったデータ消去が実施できるため、媒体に情報が残る心配がありません。
MDMサービスについて詳しくはこちら。
▼MDMサービスとは何か? 機能や必要性、法人の導入・サービス比較ポイントと選び方を徹底解説
BCP対策と業務継続性の確保
自然災害、パンデミック、サイバー攻撃など、企業活動に深刻な影響を及ぼす事象への備えとして、事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の重要性が叫ばれています。
PC LCMサービスは、BCP対策としても大きな効果を発揮します。
例えば、社員が急遽、在宅勤務を強いられた場合でも、LCMサービスのパートナー企業が迅速に代替端末を用意し、キッティング済みの状態で自宅に配送できる仕組みを持っていれば、業務を止めることなく継続できます。
また、クラウドとの連携により、端末設定やデータ環境が企業側で管理されており、使用端末が変わってもログインするだけで即座に業務を再開できるといった柔軟な運用も実現します。
災害や障害発生時に備えた予備端末の常設ストックや稼働端末の稼働状況の可視化もLCMのオプションサービスとして用意されることが一般的であり、多拠点展開をしている企業にも適したソリューションです。
PC LCMサービス導入時に押さえておきたいポイント
PC LCMサービスを導入する際には、単に業務負荷の軽減やコスト削減効果だけでなく、企業の運用体制、規模、導入目的に応じた細やかな準備と検討が不可欠です。
導入を成功させるためには、事前に自社のIT資産管理体制を見直し、LCM事業者との連携体制を整える必要があります。
対象となるPCやデバイスの選定
LCMサービスを円滑に導入・運用していくためには、まず管理・運用の対象となるPCやデバイスの範囲を明確に定めることが重要です。
具体的には以下の観点で選定を行います。
| 選定基準 | 確認ポイント |
| デバイスの種類 | ノートPC、デスクトップPC、タブレット、モバイル端末 など |
| 端末数 | 全社合計の所有台数、拠点・部門別の台数 |
| OSおよび管理対象 | Windows、macOS、Chromebookなどの比率 |
| 利用年数・入替時期 | 使用年数が経過しているPCの割合、今後のリプレース計画 |
このように対象を明確にすることで、導入するサービスの範囲や適用方針を整理できます。また、端末のライフサイクルに応じた保守・リプレース計画を立てるためにも有効です。
社内規模と運用体制に応じたカスタマイズ
中堅・中小企業と大企業では、PC管理の体制や必要とされるサポート範囲が異なります。LCMサービスの提供内容は、企業規模や管理担当者のリソース状況に応じて柔軟にカスタマイズすることが求められます。
例えば、社内に専任の情シス部門がない企業では、PCのキッティングから日常的なトラブル対応まで、包括的なサポートを外部業者に委託するケースが多く見られます。
反対に、IT部門が充実している大企業では、特定の業務(例:廃棄・データ消去)だけを外部化し、コア業務にリソースを集中させるといった活用も可能です。
次のような項目を整理しましょう。
- 自社で対応できる作業と外部に委託したい作業の切り分け
- 複数拠点への均一対応の必要性
- 24時間・365日対応や多言語サポートの要・不要
これらをベースに、標準パッケージでは不足する機能を補い、コストバランスを調整することが可能です。
信頼できる外部事業者の選び方
PC LCMサービスの導入に成功するか否かは、サービスの品質と運用体制が安定した外部事業者を選べるかに大きく左右されます。
選定においては、価格だけでなく、各社の実績や対応力を比較検討することが急務となります。
以下の観点から事業者を評価しましょう。
| 評価項目 | チェックポイント |
| 導入実績 | 同業種・同規模企業での導入実績があるか |
| サポート体制 | 全国展開が可能か、オンサイト保守に対応しているか |
| 対応スピード | トラブル時の初動対応時間、交換対応の工数 |
| 情報セキュリティレベル | ISMS・プライバシーマークなどの認証を保有しているか |
| カスタマイズ柔軟性 | 自社のニーズに合わせた設定・契約メニューの有無 |
また、委託業務にかかるSLA(サービスレベルアグリーメント)が明確に定義されているかも確認しましょう。
遅延時の対応方針、問い合わせの優先度ごとの対応時間など、運用に直結する部分まで丁寧にチェックすることが大切です。
サービスを提供するだけでなく、導入前後での業務改善提案や運用効率化のアドバイスができる外部事業者は、長期的な視点で見ても信頼性が高いといえます。
業種別の導入事例から見る効果
PC LCMサービスは、業界や業種の特性に応じてさまざまな効果を発揮します。
特に、多数のPCを日常的に運用し、セキュリティや業務効率に課題を抱える企業においては、導入の成果が明確に現れています。
以下では、主な3業種に分けて、PC LCMサービスの具体的な導入効果や活用パターンを紹介します。
製造業における保守負担の軽減
製造業では、設計部門から現場まで多様な業務にわたってPCが使用されており、用途やスペックが異なる多数の端末管理が不可欠です。
加えて、生産ラインに近い環境では、ほこりや湿度などの影響により、機器の故障リスクも高まります。
そのため、PCの定期保守や修理対応、デバイス刷新を一括管理できるPC LCMサービスの導入は、IT管理部門の負担軽減とシステムの安定稼働に大きく寄与します。
例えば、大手自動車部品メーカーでは、全国の工場に導入された1万台以上のPCを対象に、一元的なソフトウェア更新や遠隔監視を実施することで、年間500時間以上の現場対応工数を削減した事例が報告されています。
| 導入企業 | 課題 | 導入の効果 |
| 自動車部品メーカー(神奈川県) | 工場内PCの故障・対応遅延と対応人材の不足 | セントラル管理により、障害対応時間を前年比40%短縮 |
| 電子部品製造企業(愛知県) | 国ごとに分断されたPC管理体制 | グローバルITポリシー統一の推進、コーポレートガバナンスを強化 |
金融業におけるリスクマネジメントの強化
金融業界では、個人情報や取引情報といったセンシティブなデータを取り扱うため、PCセキュリティの強化は不可欠です。
加えて、PCの入れ替え・廃棄の際には、データ完全消去が求められ、法令遵守(コンプライアンス)が重要となります。
そのため、PC LCMサービスでは、HDDの物理破壊や消去証明書の発行などセキュリティに配慮したリプレース作業が活用されています。
実際に、ある都市銀行では、5,000名以上の営業職が利用するノートPCのセキュリティ強化と管理コスト削減を目的に、LCMサービスを導入。キッティング済み端末を差し替える流れを採用し、1年で80%以上のユーザーから「設定の手間が減った」との声が寄せられるなど、効率化と満足度の両立を実現しています。
| 導入企業 | 課題 | 導入結果 |
| 都市銀行(東京都) | 支店間で異なる端末管理とセキュリティ対応のバラツキ | 全社共通ポリシー準拠端末に更新、情報漏えいリスクを大幅に抑制 |
| 証券会社(大阪府) | 退社時の端末返却処理・データ抹消の不徹底 | 端末ごとに厳格なデータ抹消+証跡管理を徹底、監査対応を強化 |
PCのデータ消去証明や処分記録管理は、情報セキュリティマネジメント体系「ISMS」への対応にもつながります。
教育機関での端末管理の効率化
教育現場では、近年のGIGAスクール構想の推進により、児童・生徒に1人1台の端末を配備する体制が整いつつあり、その一括管理ニーズが高まっています(参考:文部科学省「GIGAスクール構想」)。
しかし、現場の教職員はICT機器運用に不慣れであることも多く、OS更新や生徒用アカウントの設定など、専門スキルを必要とする管理作業に負担を感じているケースも少なくありません。
LCMサービスを活用することで、キッティング・デバイス展開から定期的な保守、端末交換、さらにはソフトウェアアップデートの遠隔対応まで、包括的な支援を受けられます。
| 導入機関 | 課題 | 導入による効果 |
| 市立中学校(千葉県) | 200台の端末を各学年ごとに管理、台帳整備の遅れ | PC資産管理ソフトを導入し、Webベースで在庫・貸与状況を一元化 |
| 公立高校(神戸市) | 端末不調時の対応が遅れ、授業に支障 | 定期点検・即日代替提供の保守体制を整備し、授業進行の安定化を実現 |
導入後のアンケート調査では、89%の教育関係者が「LCMによるPC運用のアウトソーシングによって、学校全体のIT環境の品質が向上した」と回答しています。
今後のPC LCMサービスの展望とトレンド
近年、企業のIT環境はより多様化・複雑化しており、PCをはじめとするエンドポイント端末の管理に対するニーズも大きく変化しています。本章では今後さらに進化が期待されるPC LCMサービスの展望と、最新の業界トレンドについて詳しく解説します。
クラウド管理ツールとの連携
従来のPC管理はオンプレミス環境を前提としていましたが、クラウドベースのIT資産管理ツールの普及により、PC LCMサービスもクラウド連携が標準となりつつあります。
Microsoft Entra ID(旧Azure AD)やGoogle Workspaceなどのクラウド型ディレクトリサービスを活用することで、リモート環境からの設定変更やポリシー適用が柔軟に行えるようになります。
また、SaaS(Software as a Service)型のIT資産管理サービスである「Jamf Pro」や「Flexera」、「ManageEngine」などとの統合も進み、クラウドネイティブ環境に即した端末管理が可能となっています。
これにより、テレワークやハイブリッドワーク環境下でも一貫性のある端末運用が実現できます。
例えば、PCの利用状況やOSのバージョン状況をクラウドダッシュボードで即時把握できるようになり、社内のITガバナンス強化が可能となります。Microsoft Intuneを活用した端末自動登録やポリシー配布の実例も増えており、その効果は広く知られつつあります。
ゼロトラストやエンドポイントセキュリティとの融合
セキュリティ脅威の高度化に伴い、PC LCMサービスも次世代セキュリティフレームワークとの融合が求められています。
特にゼロトラスト・セキュリティの考え方と連携したLCM運用は、今後のスタンダードになっていくでしょう。
ゼロトラストでは「すべてのアクセスを信頼しない」を前提に、端末とユーザーの認証を強化します。
これにより、LCMサービス側も端末のセキュリティ状態を常時監視し、要件を満たしていない端末はネットワーク接続を遮断する仕組みが導入されつつあります。
具体的には以下のような機能の統合が進んでいます。
| 融合されるセキュリティ技術 | PC LCMサービスの提供機能 | 導入メリット |
| EDR(Endpoint Detection and Response) | 端末の健全性監視、マルウェア検知対応 | インシデントの即時検出と初動対応 |
| 多要素認証(MFA) | アカウント保護のための認証導入支援 | 不正ログインの抑止と信頼性の向上 |
| 統合ログ分析(SIEM) | PC利用履歴の一元監視と不審動作の検知 | 内部不正や情報漏えいリスクの軽減 |
これらのテクノロジーとLCMサービスを組み合わせることで、端末導入から廃棄までの一貫したセキュリティ対策がより充実したものとなるのです。
テレワーク需要とモバイル環境への拡張
新型コロナウイルスによる働き方の変化が引き金となり、多くの企業でテレワークや在宅勤務が常態化しました。
今後もこの流れは続くと予想され、それに伴ってLCMサービスの対象がPCだけでなく、スマートフォンやタブレットといったモバイルデバイス全般に広がりつつあります。
また、テレワーク環境下では、従業員の自宅への端末配送や、郵送によるリプレース、遠隔地からのヘルプデスク対応、VPNやVDIによる業務環境の整備など、従来の対面対応ではカバーできなかった領域への対応も求められています。
このニーズに対応するため、多くの外部事業者が「リモートキッティング」や「ゼロタッチ導入(Windows Autopilot)」に対応したサービスを展開しています。
さらに、BYOD(Bring Your Own Device)やCYOD(Choose Your Own Device)といった柔軟な端末選択制度もLCMサービス領域に組み込まれ、セキュリティと利便性を両立させる取り組みが加速しています。
こうした背景から今後のPC LCMサービスは、「働き方の多様化」に柔軟に対応し、導入初期から廃棄に至るまでデバイスのライフサイクル全体をリモートで完結できる体制が重要になると考えられます。
BYODについて詳しくはこちら。
▼BYODとは? セキュリティ対策、効率的な活用ポイント、メリットやデメリット、導入事例を解説
まとめ:PC LCMサービスは業務効率化に寄与
PC LCMサービスは、IT機器の導入から廃棄までのライフサイクルを一貫して支援し、コスト削減やセキュリティ強化、業務効率化に寄与します。
特にPCの資産管理やヘルプデスク機能を外部委託することで、IT部門の負荷を軽減しつつ安定した運用が可能です。
セキュリティ面では、データ消去や最新OSの適用によりリスク軽減が期待できます。IT資産管理やPCのLCMにお悩みの際は、テクバンまでお気軽にご相談ください。
テクバンへ相談する